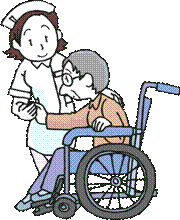|
|
|
トップページ>専門部より>看護改善委員会より 去る11月23日(日)、雄勝中央病院・リハビリテーション室において、秋厚労第15回看護ゼミナールが行われました。講師は同院のリハビリ副技師長の坂田徳隆さん、テーマは「わたしにも出来る、ちょこっとリハビリ」。参加者(31人)は、交代で患者さん役にもなり、寝返りや起き上がりなどに要する身体のメカニズムを再認識しました。 身体のメカニズムを再認識 今回の看護ゼミは、午前中が講演、午後が実技というプログラムで行われました。講師の坂田さんは、「障害者へのディズニーランドの対応」などの話題も交えながら、わかりやすく、楽しいお話をなさいました。家族のお話をするときは顔が緩みっぱなしで、人柄の良さをうかがわせました。 また、日々の仕事の中で、看護師が、理学療法士に「患者さんを早く座らせてください」と依頼することがあるそうです。でも、股関節が70度以上曲がらないと「座る」という行為はできません。そのようなときは、関節を動かすところから始めます。坂田さんは、看護スタッフが、ちょっとした身体のメカニズムに関する知識を身につけていることの大切さを強調します。 さらに、「リハビリ180日制限」などにも触れ、今日のリハビリが抱える問題点もチクリ。 介助はあくまでもお手伝い 午後からは、寝返り・起き上がり・立ち上がりをテーマに、グループをつくって実技を行いました。 仰向けに寝て、組んだ両手を前方に突き出し、首・手の順に上半身からひねると寝返りを打つことができます。介助をする人は、軽く押すなど、少しだけお手伝い。横を向いたまま、ベッドから足を出して、身体を起こすことができれば「座位」になります。このときも、患者さんの軸手に介助者が手を添えて、どこに力を入れたらよいかを確認した上で、起き上がる方向を示すように身体全体を使ってゆっくり介助します。ベッドに座っている人が、お辞儀をするように、頭を前方に出すことができれば、立ち上がったり、車椅子に乗り移ることもできます。 基本は、本人の力を最大限に発揮してもらい、介助はあくまでもお手伝いに徹すること。力に任せて患者さんを車椅子に乗せようとして、うまくいかないばかりか、介護者が腰を痛めた事例もときどき耳にします。でも、思ったよりも、患者さんは自分で動くことができるそうです。「リハビリで立ち上がる訓練をしていた患者さんが、病室では平気で歩いていた」という笑い話も紹介しながら、ゼミは楽しく進行していきました。 毎日のヒントになる 参加者の感想アンケートには、次のような言葉がありました。「寝返り、起き上がりはよく行うため、とても勉強になりました。今まで力まかせの感じだったため、今回学んだことを生かしたいです」「毎日のヒントになると思う」「これをマスターできたら、(仕事が)楽しくなる」などなど。学ぶことの楽しさを素直に表現したものばかりです。
|
|
Copyright 2006 © Akita Koseiren Union .Allrights Reserved.